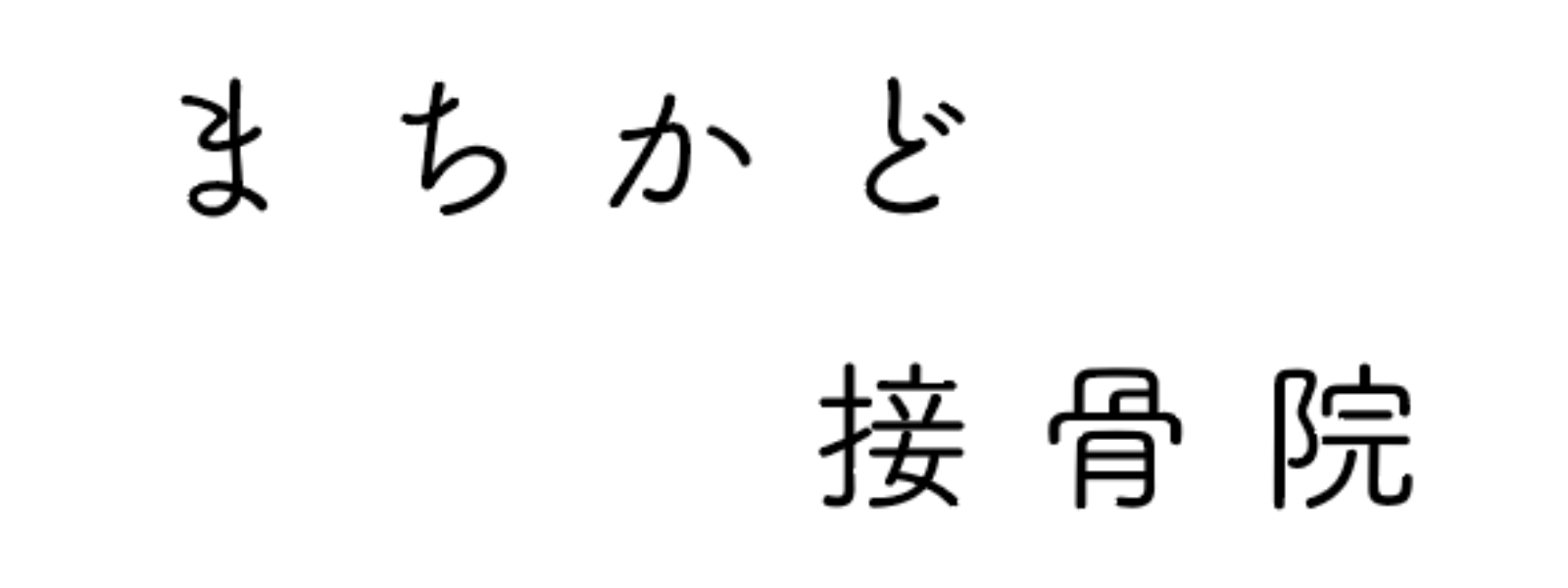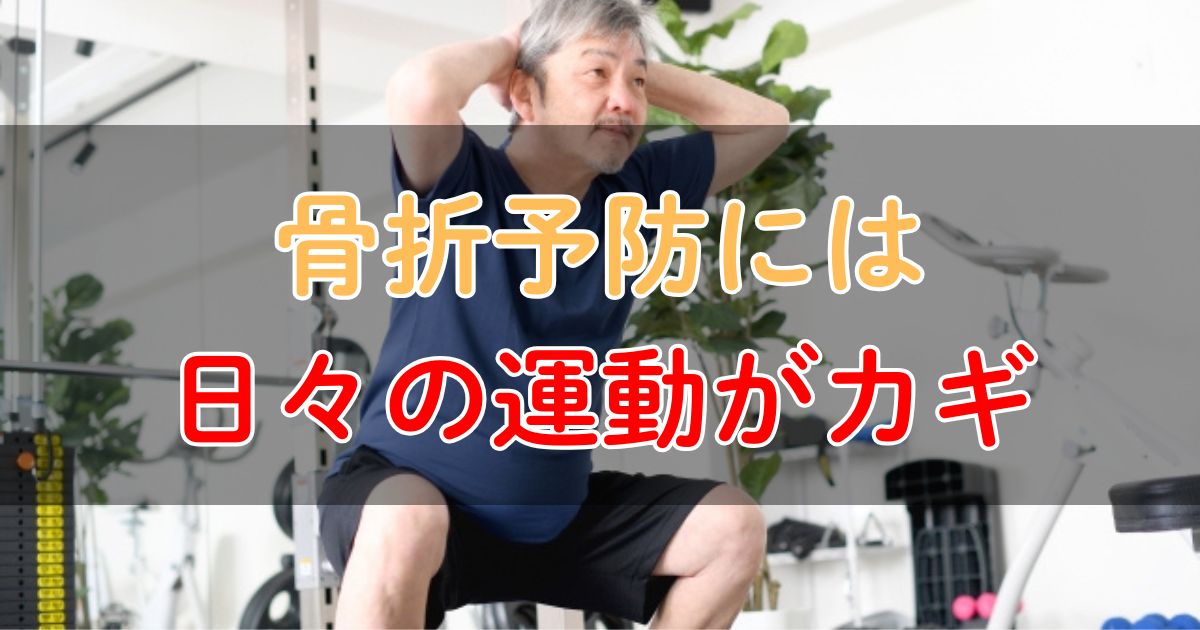年齢を重ねるにつれて、「骨がもろくなる」「骨折しやすくなる」という話を耳にすることが増えます。特に中高年以降、骨粗しょう症の進行によりちょっとした転倒や軽い衝撃で骨折してしまうケースが多くなります。
厚生労働省の調査では、日本には40歳以上で 約1,600万人 の骨粗しょう症患者がいると推計されています。特に女性は閉経後にリスクが高まり、70代では3~4割の方が骨粗しょう症と診断されるというデータもあります。
さらに心配なのが 骨折 です。特に大腿骨の付け根の骨折は、年間で 16万人以上 が発生しており、多くは「立っている高さからの転倒」で起きています。骨折は長期入院や介護につながる大きな要因です。
しかし、予防する方法もあります。
代表的なのは 運動療法 です。筋肉や骨に刺激を与えることで骨密度を維持・改善し、転倒防止にもつながります。さらに、栄養(カルシウムやビタミンDの摂取)や生活習慣の見直しも重要です。
このブログでは
- 年を取ると骨にどんな変化が起きるか
- 運動療法で骨を守り、骨粗しょう症を改善する方法
を、論文を引用しながら整理していきます。
年齢を重ねると骨にはどんなリスクがあるのか
骨密度の低下
- 加齢に伴い骨を作る「骨形成」より骨を壊す「骨吸収」のほうが優位になることが多くなります。
- 女性の場合、閉経後ホルモン(エストロゲン)の低下によって骨密度の低下が加速します。
骨の質・構造の悪化
骨密度だけでなく、骨の内部構造(骨微細構造)が劣化することも重要です。
- 骨梁の細さ・分離などの構造的な問題。
- 皮質骨における孔の増加など。これにより骨の強度が下がる。
骨の質以外の要因も影響する
骨折リスクは骨密度だけでは決まりません。他にもさまざまな因子が加わります。
- バランス能力の低下 → 転倒しやすくなる。
- 筋力の低下(筋肉量・筋力双方)→ 骨にかかる負荷が減ることで骨刺激が少なくなる。
- 栄養不足(カルシウム、ビタミンDなど)、喫煙、過度のアルコールなど。
骨折とその影響
骨折は単なる痛みや入院だけでなく、その後の生活の質(QOL)、死亡率にも関わります。
- 50 歳以上の女性の約50%、男性でも20%が骨粗しょう症関連の骨折を経験する可能性があると推定されています。
- 股関節骨折は特に重く、 寿命や生活機能低下につながることが多い。
参考文献:Aging and bone loss: new insights for the clinician・Ageing-related bone and immunity changes: insights into the complex interplay between the skeleton and the immune system・Exercise for Postmenopausal Bone Health – Can We Raise the Bar?・Osteoporosis and fracture risk in older people
運動療法で骨粗しょう症・骨折リスクをどう改善できるか
骨は「力学的な刺激(メカニカルストレス)」に反応して強くなる性質があります。筋肉が収縮して骨を引っ張る力や、歩行・ジャンプなどで骨に加わる衝撃が刺激となり、骨芽細胞が活性化します。この刺激によって骨の新陳代謝が促され、骨量の維持・増加につながります。この考え方は Wolff(ヴォルフ)の法則 と呼ばれています。
では、「運動」でできること、科学的に証明されていることはどんなことがあるのでしょうか。
運動の種類と効果
いくつかのタイプの運動が骨に良い影響を与えます。
| 運動タイプ | 効果 |
|---|---|
| 高強度抵抗運動+インパクト運動 | 腰椎の骨密度を増加させる報告あり。 |
| 中~低強度の荷重運動/重力負荷をかける運動 | 骨密度低下の速度を遅らせる。 |
| バランス訓練・転倒防止運動 | 転倒そのものを減らすことで骨折リスクを下げる。 |
Exercise therapy for osteoporosis: results of a randomised controlled trial.
Aging and bone loss: new insights for the clinician
運動の頻度・強さの指標
- 高強度運動:抵抗運動では 1RM(1回だけ持ち上げられる重量)の80%以上、反復回数は少なめ(例:8回以下)など。
- インパクト運動:地面反力が体重の数倍に及ぶようなジャンプ・ステップなど。
- 実施期間:8か月以上の継続が効果を示した研究がある。
参考文献:Exercise for Postmenopausal Bone Health – Can We Raise the Bar?
最近のエビデンス
・「骨折を経験した患者」に対し、適切な運動処方が骨密度を有意に上げることが示されました。
・閉経後女性で 高強度抵抗運動+インパクト運動プログラムを 8 ヶ月間行ったところ、腰椎の骨密度がおよそ 2-4% の増加を示し、従来の低~中強度運動と比べて改善が大きかった。
参考文献:Exercise for Postmenopausal Bone Health – Can We Raise the Bar?・The efficacy of exercise prescription in patients with osteoporotic fractures: a systematic review and meta-analysis
推奨できる運動療法の具体例
運動プログラムの構成案
| 週あたり頻度 | 内容例 |
|---|---|
| 2〜3 回 | 抵抗運動(重りを使ったスクワット、レッグプレス等) |
| 1〜2 回 | インパクト運動(段差昇降や小ジャンプなど、安全性を確保できる範囲で) |
| 毎回 | バランス訓練(片足立ち、歩行中の方向転換)。転倒予防が非常に大切 |
| 継続期間 | 少なくとも半年〜1年以上。骨の新陳代謝を考えると時間が必要 |
その他の生活習慣アプローチ
- 栄養:カルシウム、ビタミンD を含む食事。必要であればサプリメントも検討
- 日光浴などでビタミンD合成促進
- 禁煙、過度のアルコールを控える
- 体重管理(特に急激な体重減少は骨量低下を招くこともある)
実践上の注意点
- 骨折リスクが非常に高い(過去骨折歴あり・骨密度非常に低いなど)場合は、運動プログラムは医師と相談の上で。無理なインパクト運動などがかえって危ないこともある
- 正しいフォームで行うこと。間違った動作は関節を痛めたり、逆に骨に負担をかけてしまうことがある。医療機関、トレーナーでの指導が重要
- 継続性が鍵。数週間だけで終わらせず、習慣にすること
- 痛み・違和感の有無、進捗を定期的にチェック。必要に応じて強度調整
まとめ
- 年齢を重ねると骨密度・骨質が低下し、骨折リスクは確実に上がる。特に閉経女性や高齢者ではその進行が顕著。
- 運動療法、特に高強度抵抗運動+インパクト運動、バランス訓練などは、「腰椎などの骨密度を増加させる」「転倒予防」で骨折リスクの軽減が期待できる。
- 運動だけでなく、栄養・生活習慣の改善、定期的な評価がセットであるとより効果的。
当院では、年齢を重ねても「自分の骨で歩ける」「転倒しても骨折しにくい体」をつくるお手伝いをしています。気になる方はお気軽にご相談ください。